虎の尾を踏んでしまったのか、それともパンドラの箱を開けてしまったのか。そもそもライトノベルにおける学園ラブコメ史を探っていたはずなのに、勢い余って『ブギーポップ』について書いたのが間違いだったのでしょう。

今回はその記事をキッカケとした、色々なコメントやつぶやきに対する、私なりの回答を書きたいと思います。元となる記事は、↓これです。

そもそも読んだこともない作品のことを、やや批判的に書いたことが間違いでした。ただし、内容に対する批判はしておらず、後続への明らかな影響がその時の私には見えないことを述べたつもりです。実はこの記事については、私自身あまり拡散してほしくなくって、この記事を書いたときにtwitterにもつぶやきませんでした(その1と3は書いたことをつぶやきました)。
それがはてなブックマークに登録され、そこからこの記事を見に来る人が現れました。17件あったブックマークのコメントを見ると、きちんと読んでくれている人もいればそうでない人もいるなぁというくらいの感想。なお、はてブに登録されたことに対し、なんとも思っていませんので。今後も登録していただけると嬉しいです。

さらにその後、7/9~10くらいでしょうか、仕事明けにtwitterを見たら、ブギーポップの話題がちらほら。その元をたどっていくと、『ブギーポップ』のラノベ史上の影響云々というのがあって、どうやら私の記事がキッカケになったようだなと。
90年代末に『ブギーポップは笑わない』がヒットした頃、異様な憎悪を向けたり影響を矮小化しようとして、00年代に入るとアンチ『ファウスト』になったラノベファン(だいたい富士見ファンタジアの読者)がいたんだけど、久々にそういうひとを見て懐かしくなってしまった。https://t.co/hEaEpV7ngH
— ゆずはらとしゆき (@yuz4) July 9, 2022
ブギーポップに影響を受けたラノベがないっていうのはどうかな。
まず、記事内で触れられてる西尾維新や那須きのこ
は厳密にいうとラノベじゃないし…って話は、00年代前半はラノベ史上でも特にラノベ定義のコアが高年齢化していた時期なので、ジャンル外の出来事として切り捨てる必要はないと思う。— hatikaduki (@hatikaduki) July 9, 2022
いろいろなつぶやきを読んで、ずいぶんと勉強になりました。やはり読まずにアレヤコレヤいうのは良くないなぁと思いつつも、こうやって議論(プチ炎上?)することで、様々な意見や当時の記憶が聞けるのは嬉しいことですし、記事を書いた意味はあったのだなと思っています。
私は研究者ではありません
まず、はてなブックマークにあったコメントで、
【妄想ラノベ史】ライトノベルにおける、不思議要素のない学園ラブコメを探る。その2【97~99年】
観測してないものを、指摘後も観測しない(不可能ではない)のでは「自分の都合いいところに着地させよう」という意図しか感じないので、研究者ではないよね。
これはまさしくそのとおりで、私は研究者じゃありません。ただ単に90年代ラノベに学園ラブコメがなかったのかという疑問をキッカケに、ラノベの歴史を調べてブログに書いただけのものです。そもそも読まずに書いたのは間違いだったのですが、ラノベの歴史について書かれた本やサイトは読んでいて、それらのなかで語られる『ブギーポップ』の後続への影響に疑問を持って書いただけです。
居酒屋で酔っ払ってラノベ論を語っている親父の戯言くらいに思っていただければ幸いです。
『ブギーポップ』フォロアーは?
件の記事で一番の問題点は「『ブギーポップ』フォロアーは?」という項目でしょう。ここで私が一番述べたかったのは、「ラノベ史に関する話に『ブギーポップ』の名前が挙がる度、それほど後続のラノベに影響をあたえたのか?と思う」ということです。なお、ここでいうラノベとは、「80年代末の角川スニーカー文庫、富士見ファンタジア文庫を始まりとする、表紙や口絵・本文にイラストのある、10代の少年向けエンタメ小説」で、最狭義のラノベです。
ここで私の考えをもう一度。
『ブギーポップ』の影響を受けた作家として挙がる西尾維新や奈須きのこの作品は、ノベルス作品であって厳密にいうとライトノベルではないと思っています。これに関して定義を狭くして、西尾維新や奈須きのこ作品に言及しないのは意味がないというコメントも見られるわけですが、そこに違和感を感じるわけです。
ラノベでなくってマンガで考えてみてください。少年漫画の歴史を考えるとします。少年ジャンプやサンデー、マガジン、チャンピオンあたりを中心に考えていると。それでその少年誌で大ヒットした作品があって、それに影響を受けたという作家が青年誌に作品を発表したと。これも大ヒットして、青年誌において大きな流れになったとします。
おおもとの大ヒット作はマンガ史に残る作品ですし、大きな流れを作った作品と言えます。しかし、少年漫画においてそれらの影響を受けた作品が見られなければ、少年誌の流れを変えたとまではいえないのではないか? ということです。
もちろん影響を与えるというのは、目に見えるものだけではないので、それをどうこう言うのは難しいものなのですが、似たような傾向を持った作品、劣化〇〇なんて呼ばれる作品があってもおかしくないのではないかと思うのです。
ラノベに話を戻すと、ラノベの定義があやふやでノベルスはラノベなのか? という問題にあたります。かりにノベルスをラノベに含めるとしたら、80年代からつづくノベルスの歴史をラノベの歴史に含める必要が出てきます。また、90年代のメフィスト系の作家にも触れなくてはなりません。それらに触れずに『ブギーポップ』の影響を受けた作家の作品として、都合よくこのときだけノベルス作品をピックアップするのはおかしいなと思ったわけです。
最狭義のラノベ作品のヒットが、やや広義のラノベに影響を与えたのは良いとして、最狭義のラノベへの影響が知りたかったわけです。このあたりがラノベ解説本やサイトでははっきりとしなかったので、もう少し具体的な作品名が挙がっているとわかりやすいのになと。でも、書き方が悪かったですね。『ブギーポップ』がラノベ史上で全く影響を与えていないと言っているように受け取る方もいらっしゃったみたいなので。
特に「そのわりには『ブギーポップ』フォロアー的な作品は見当たりません」と書いたのは、浅はかでした。これにはtwitterであった、「影響を与えた」≠「近い作風になる」というのが言われてみれば正しいと思っています。80年代末から90年代始めにかけてのラノベでは異世界ファンタジーが溢れたことや、『涼宮ハルヒの憂鬱』が大ヒット(特にアニメ)してからキャラの立った女主人公や謎部活作品が溢れたことで、ラノベにおいてはヒット作の影響が見えやすいという先入観が出来上がっていたのだなと。
『ブギーポップ』が最狭義のラノベに与えた影響
というわけで、様々なコメントやつぶやきから、『ブギーポップ』が与えた影響を。一番大きいのは、『灼眼のシャナ』『とある魔術の禁書目録』へと続く、学園異能バトルの源流だということでしょうか。
もう一つ具体的なタイトルが挙がっていたのが、うえお久光『悪魔のミカタ』。こちらはミステリ的な作品か。
それ以外にもパッケージ(装丁)的な部分や、新人賞応募の動機への影響などなど。
もう一つ忘れてはならないのが、セカイ系への影響。セカイ系はいまいち定義のよくわからない言葉ですが、↓こちらの記事でなんとなく理解できたような気がします。
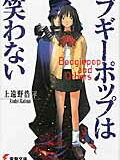
となると『イリヤの空、UFOの夏』、ひいては『涼宮ハルヒの憂鬱』への影響まで考えられますでしょうか。ハルヒがセカイ系なのかどうかはよくわかりませんが。
今後読むべき本
というわけで、今回は非常に勉強になりましたってことで。ところで実は一番心に響いたコメントがありまして。
【妄想ラノベ史】ライトノベルにおける、不思議要素のない学園ラブコメを探る。その2【97~99年】
ブギーポップ未読なら論の中心に据えずさらっと流せば良かったのでは……
これに限りますね。勢いで書いちゃうのは良くないですね。というわけで、今後きちんと『ブギーポップ』は読みたいと思っています。それと同時に『ブギーポップ』に関する書籍が紹介されていたので、これも読むことにします。






