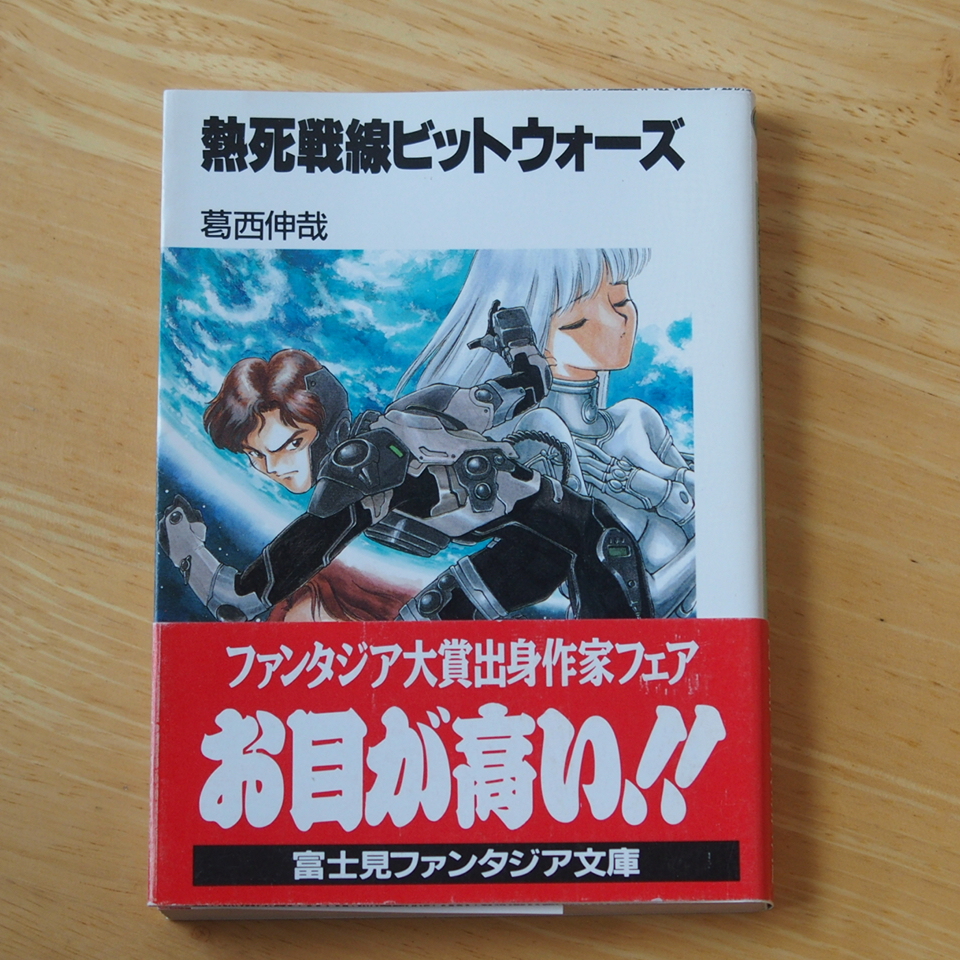さて、今回の「90年代単巻ラノベを読む」は、90年代富士見ファンタジア文庫単巻モノを読んでいる中で出会った作品です。一般的な知名度は低いですが、これは面白いと思ったので、取り上げることにしました。
熱死戦線ビットウォーズ
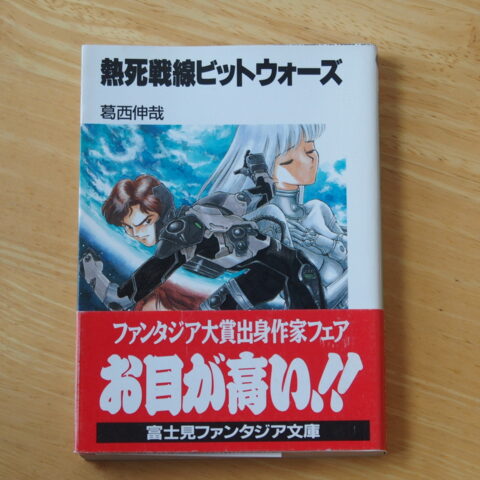
著者:葛西 伸哉
イラスト:小野 敏洋
文庫:富士見ファンタジア文庫
出版社:富士見書房
発売日:1995/01
私立誠鵠館高校の三年生上沢鏡一は、夕暮れの公園で一心にフルートを奏でる美しい少女、美環と出会った。その時、少女の前に黒いレザーの上下を着た男が現れ、二人は一瞬の閃光の後『変身』していた。鏡一は偶然にも、地球の存亡をかけた「ビット」たちの闘いに巻き込まれてしまったのだ。空間や物質のエネルギーを、精神の力で切り取り変換させる能力を持った者たち―彼ら「ビット」たちの闘いに巻き込まれた鏡一は、自らの「ビット」能力に目覚めた。彼は愛する者のため、自らも闘うことを決意する。
読んだ感想
80年代後半から90年代にかけて、特撮変身ヒーローオマージュ作品がマンガやライトノベルでいくつかあったように思います。印象に残っているのは、マンガでは『強殖装甲ガイバー』、ラノベでは『ミュートスノート戦記』『俺の足には鰓がある』などです。
こういった作品が出てきたのは、70年代の「仮面ライダー」シリーズなど特撮変身ヒーローモノを見て育った人が、マンガやラノベの送り手側になったためでしょう。
今回取り上げる『熱死戦線ビットウォーズ』もあらすじや口絵から、それらのひとつくらいの印象で読み始めました。ところが、これが変身ヒーローオマージュで終わっていませんでした。
変身ヒーローモノといえば、改造などによって特殊な能力を与えられたものが、世界征服を狙う悪の組織と退治するものが定番です。しかし、『熱死戦線ビットウォーズ』はそうではありません。この作品において、主人公の少年は戦いの中に巻き込まれることで、特殊能力を身につけます(もともと持っていたものが顕現するといったほうが良いかも)。そして、戦う理由も正義を守るためというわけではなく、特殊能力者のバトルロイヤルです。今風に言えば、デスゲーム。
敵対する勢力は悪の組織ではなく、同じ特殊能力者。相手を倒すことで自身に力を取りこむことができるので、お互いが戦い合っているわけです。最後に残ったものは最強の力を持つことができます。そして、この戦いの裏で糸を引いているものが目指すのは、この能力を使った宇宙の改変。物語は壮大です。
ちなみに作中での宇宙の範囲は地球から約39万kmで、それより外は「ホワイトノイズの海」という設定。こういった設定も面白いです。ただのヒーロー物に見せかけておいて、この展開には惹き込まれてしまいました。ちょっとハードSF的な理屈っぽさがあるので、その当たり苦手な人がいるかも知れませんが。
物語自体も面白いのですが、キャラクターやその能力も魅力的です。主人公を始めとする特殊能力者はアイテムを使って「変身」します。今となってはアイテムを使った変身って普通かもしれませんが、90年代序盤ではアイテムを使っての変身はあまりなかったように思います。仮面ライダーから始まった変身はおもに、一定の動作をすることで変身したわけです。最近の仮面ライダーでは、アイテムをベルトにセットするタイプが多いのでしょうか。
この作品では、アイテムを持って念ずる(意識を集中するような感じです)と変身します。その変身時の描写のカッコよさよ!
フルートをアイテムとするヒロインの変身はこんな感じ。
美環はフルートを構えた。艶やかな金属管が液体のように延び広がり、彼女の身体を呑みこんだ。スカートや袖の余裕あるシルエットがプラチナ色の皮膜に包まれて、ボディラインへと引き絞られる。(p.74)
私が一番気に入っている、『文字使い』の麻由子の変身シーン。
「あたしは麻由子——『文字使い』の麻由子!」
その手の中の辞書がバラバラにほどけ、それぞれのページが風に吹かれるように激しく 渦を巻く。
思わず顔をかばう鏡一たちが嵐の鎮静を感じて視線を上げると、そこにはスキンタイトな〈鎧〉に身を包んだ麻由子がいた。髪や瞳もメタリックな濃紺に変化し、顔にも奇妙なマーキングが浮かんでいる。コスチュームの表面では数えきれない文字が、コンピュータ・グラフィックスで描いたかのように絶えず形を変えながら蠢いていた。
このスタイルが、麻由子の意識によって具現化した彼女の武装なのだ。(p.143)
これ今読むと、平成仮面ライダーのCGバリバリの変身シーンを思い浮かべますけど、これ書かれたの94年ですからね!
デスゲーム最後の敵は、携帯ゲーム機を変身アイテムにしています。面白いのがその能力。
終也の手が店内の筐体に触れると、画面から光の泉が吹きあがった。それは瞬時にひとつのかたちを形成していく。
長身の筋骨 たくましい青年。空手の道着のようなすりきれた服にハチマキ、裸足。
そいつは、鏡一もよく知っているビデオゲームのキャラクターだった。
その男が両手を腰だめに引き絞って、エネルギー球を打ち出した。音もなく直進する光球が鏡一の頬をかすめて飛び、後方の壁を打ち砕く。
現われたのはその格闘戦士だけではなかった。
隻眼で二刀流の侍、コウモリの翼を持った美しい女モンスター、背広姿に長い棒を構えたサングラスで禿頭の男、アポロキャップを被った金髪の若者……。
十数人のさまざまな姿をした人間が、さほど広くない店内に出現した。(p.179)
ビデオゲームの様々なキャラクターが現実化して、新宿の街を舞台に大暴れするのですが、新宿アルタの大型モニター画面から戦闘メカが登場するシーンに至っては、アメリカの街をパックマンなどのゲームキャラクターが大暴れする2015年の映画「ピクセル」を思い出しました。もちろん、こちらの作品のほうが先です。
物語の展開もキャラもその描写もよくって、さらにさらに章題もかっこよいのです。
プロローグ
1.真夏の銃声
2.超人たちのゲーム
3.真夜中のエレクトリカル・パレード
4.白く果てしない海
5.逃れえぬ言葉の罠
6.新宿デジタル・バトル
7.いくつもの岐路の彼方
エピローグ
「逃れえぬ言葉の罠」や「いくつもの岐路の彼方」のタイトル、フレーズとしてもかっこよいけど、内容にもピッタリハマっていて良いんですよね。
まとめ
90年代の富士見ファンタジア文庫の単巻モノをここ最近、続けて14作品ほど読んだのですが、当時から評判の高かった『神々の砂漠 風の白猿神〈ハヌマーン〉』と並んで、最高に面白い作品でした。ハヌマーンはラノベの歴史に名前がちょくちょく登場するのですが、ビットウォーズは忘れ去られた作品のように感じます。なんてもったいないと思った次第です。
ただ、この作品を若い人が読んでも、私が感じた斬新さは当たり前のものとして感じてしまうかもしれないのかな、と思ったりもします。